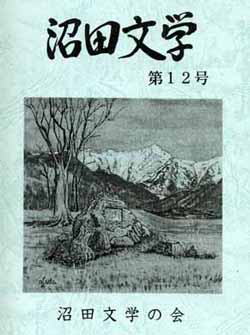沼田文学 第16号2010.6.3
小野 啓子
一番
一番好きな花は?と聞かれ
思い悩む
アネモネ 桜 芙蓉に合歓
ほかにも都忘れ 花菖蒲
絞り切れない
買い物帰り
思わず足を止める花屋の店先
みごとな蘭の株
一鉢5千円
さすがに高いなと思う
ふと目にした紫陽花
今まで見たこともない新種の花
一鉢5千3百円
でも これは欲しいという
揺るがない思い
そうか
紫陽花だったのか
値段で知った
本当の気持ち
予定外
庭先で宅配の配達員さんに会い
挨拶する
玄関に入り戸を開ける
下の娘は
消えかけのパソコンに手をかけ
待ち切れず腰を浮かせている
長女は届いたばかりの小包を抱え
たのんでおいたCDが来たけど
テストが済んでから聞くことにするよ
そう言いながら自分の部屋にかけ込む
別に何をとがめるつもりもないのに
今日一日売店にいる筈の人だった
忘れ物をとりに戻っただけなのに
仕事がんばって
気をつけてね
上ずった声で送り出す二人
車に乗り込みハンドルを回しながら
今頃二人 顔を見合わせ
驚いたねと話しているのだろうと
想像し苦笑する
五月
昼下りの暖かさ
南国風の風鈴が
時々気まぐれに唄い
テーブルには熱いハーブティー
悩める静かな部屋の中
天井に床に
壁を切り 柱に沿って
やみくもに
糸のように曲線を描く蝿一匹
羽音もなしに
不協和音を五線譜に乗せていく
目で追い回すと
背景の色に
消えたり 現れたり
集中力をかき乱す
小さな侵入者
答を求める
柔な心にまで落書きをする
沼田文学 第15号09.6.3発行
春の夜に
小野啓子
慣れぬ表情で
休み時間
飛び回り 転んで泣いたり
毎年の出来事と楽しむように
新たな一年生を迎えている
校庭の古木 ソメイヨシノ
昼のにぎわいを
消し去る闇の中
仄かに花を咲かせている
寂しそうに見えて
ほっと一息ついているのか
時々吹く風に枝を揺らし
花びらを散らし始める
静かな夜に
相対する命
花明りの中
私は一粒の種のように影となる
茗荷
小野啓子
立秋を過ぎ
毎年収穫時をのがしてしまう茗荷
今年は花を咲かす前に
大きなボール
山盛り一杯取れた
ごみを取り
ザルに移し
洗い桶の水を替え
4〜5回洗う
茗荷を薄く小口切り
きゅうりを短く千切り
しらすと一緒にご飯に混ぜる
それだけでとても美味
確かにそういっていたのに
ご飯のままか
酢飯だったか
りんごの仕事を手伝いながら
教えてくれた
作る時
いつでも教えてもらえると
書き留めてもおかなかったのに
蜘蛛膜下出血で
逝ってしまった
もう 呼びかけても
振り向いてくれる笑顔はない
桜色の茗荷
つややかに
気高い香りを放っている
旅
小野啓子
夏休みの家族旅行
訪れた松島
日本三景
遊覧船の島めぐり
松尾芭蕉 伊達正宗も
感動の句や言葉を残した
大小様々 松の島
こういう所に住んでみたいと
口々に言ってみるけれど
美しい所に住んでいても
私達と変らぬ
毎日の暮しがある
地を這う青虫が
蝶に変身したように
日々の暮しを離れ
車で一泊二日
束の間の旅人となる
気持ちが軽く羽ばたいて
遥か芭蕉の時代までも
飛んで行けそうな気がする
沼田文学 第14号08.5.25発行
雨上がり
跳び越えられるほどの
澄んだ水溜り
なまめかしい白い体を
殻から放り出すように
息絶えた
何より似合う
カタツムリの季節
溢れかえった雨水に溺れた
容赦なく奪われた
声無き命
今 水鏡の青空に
吸い込まれ
何事も無かったように
紫陽花が色めく
静かな雨上がり
朝
今年一番の寒さで
柿の葉が 一気に落ちた
庭一面
黄色やオレンジの葉っぱの海
芸術だ・・・・・
まるでゴッホのひまわり
何千何万もの
積み重なった葉
私は竹箒で
ひまわりの花びらを掃き集める
厚くなった葉の重み
力いっぱい箒を押し動かす
丸く回りから掃き集め
庭の中に
小高い錦の山が 朝日に輝く
老化
人の名も
言葉も出てこず
あれ それ
口ごもる
いつか そうなる時が来る
何人もの人から聞かされていたこと
この身を持って実感している
連続ドラマを見ても
若い主人公より
その母親の気持ちに共感している
結婚して二十五年を
直滑降で滑り降りた気分
時の経過を
早く感じる事は
良い滑りだったとも言えるか
全ては
人の歩むべき順路なのか
科学の進歩で
どう 抗ったとしても
いつまでも 年寄りが幅を利かせていたら
若えてえが かなわねえがね
二十年も前
今の私の歳だった人が
冗談交じりに笑って見せた
あの声が また聞こえる
沼田文学 第13号
叫び
ムンクの絵の中
その人物は
自然の中を貫く 大きな永遠の叫びを聞き
恐れおののいている
今年 林檎畑に
熊の気配があった
足跡と糞が数箇所
沼田インターから車で2〜3分
我が家の庭にも 小熊が現れた
見た人がいるのだ
真っ黒な犬のような小熊が
跳ねるように走って行ったと
広いゴルフ場
植林した杉や檜
雑木林が減り
今年は山の実も不作だという
天啓なのか
思わず両手を頬に当てる
新聞によれば
この秋
沼田地区103頭
群馬県内
合計325頭の熊が捕殺された
献立
やっぱり
自分の為ではだめなのだ
一人の食卓では
美味しいと驚く
喜ぶ顔が見たい
その為なら
意欲が湧いてくる
面倒な手順さえ
苦にならなくなる
季節の味を取り入れて
旬を味わう
どんな献立にしようか
あれこれ迷いながら考える
毎日の
悩みの種だと思っていたのに
一人留守番して思い知る
あれは楽しみ 笑顔の元だったのだ
思春期
少女から 娘への道のりを歩み始め
言われなくても髪をとかし
服にも自分の好みを主張する
顔の造作やスタイルも気になる様子
生まれる前は
五体満足であることを願い
元気な産声と顔を見て
安堵と喜びに涙が溢れた
あれから十三年
肩を並べるほど大きくなった
女優さんの澄んだ瞳を見て
羨ましいと
今でも感じる 自分の気持ちからしても
娘も
同じような気持ちを 抱くことだろう
それでも
心の内は 顔にも態度にも表れる
心を豊かに磨くこと
そう話してくれた 教師の言葉を
ずっと信じている
娘にも伝えたい
健康であること 心も体も
今でもそれが
幸せの証であることに 変わりは無いはず
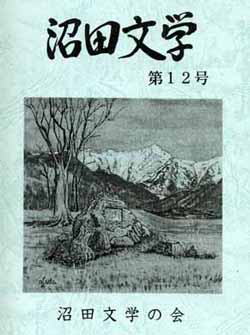
早春 小野啓子
三月
弥生の雨
初恋の涙雨
根雪を解かし
屋根の雪を落とす
梅の蕾をふくらませ
草の芽を起こす
卒業 別れ
雨音は 小さな傷口を癒し
新たな季節の 訪れを告げる
旬の味
りんごをテーブルに置く
伸び伸びと 大きく
つややかな赤い表皮
どこから見ても立派な色形なのに
一円玉ほどの黒点がある
そこから腐り始める病気で
売り物にはならない
注意して手をかけても
変形 さび 病気 害虫
規格外 被害果は沢山でる
りんごに限らず
どんな作物でも同じこと
夕食後
傷を取り除き
洗って皮付きの4等分に切る
香り高い
とびきりの旬の味
食
除草剤をまくと
草は全て枯れ果てようと
枯れずに生き残っている
科学という手で操作され 作り出された
花が咲き
遺伝子組み換えの実が成るのだ
エサとして モルモットに与えると
早死にすると噂のある不気味さ
遠ざけようとしているのに
知らぬ間にそばにいて
忍者のように姿をかくしひそんでいる
望まざるにもかかわらず
すでに口にしているのかもしれない
農家というのに
自給自足の知識も 技術も手間もなく
野菜の何から何まで
スーパーで買い求めている
見ばえのしない
昔からの食べ物が
体にいいと言いながら
子供たちを守るべき私自身が
自分の足元の危うさを
知らずに歩いている
料理に込める暖かな気持ち
健康への願いを
冷ややかに見下す悪意さえ感じる
食べることの大切さを
知れば知る程 感じる恐怖感
美食三昧の暮らしの中で
日々成長し続けている

―童 話―
みっちゃんとブンちゃん
小野 啓子
三、注射なんか大嫌い
みっちゃんと、お母さんは、うさぎさんのいる、お友達の家に遊びに来ました。そこには、みっちゃんより大きい、3才の陽気ちゃんという女の子がいます。
玄関のベルを押すと 陽子ちゃんも、陽子ちゃんのママも走って来てドアを開けてくれました。
「どうぞ、いらっしゃい。」
陽子ちゃんは大きい元気な声で言い、みっちゃんの手を取って、せかすように部屋に案内してくれました。みっちゃんが来てくれたことが、とてもうれしそうでした。
みっちゃんは、肩にかけたピンクのバックの中にブンちゃんが入っているのが気になっていました。
陽子ちゃんのママは、お茶とお菓子を出してくれました。
みっちゃんは、バッグの中から、さっそくブンちゃんを出して、お皿の中のクッキーを一つもらい、最初にブンちゃんの口に持っていき、食べさせてあげて、
「ブンちゃん、おいしい?」
そう言ってから、自分でそのクッキーを食べました。
「おいしいよ。」
みっちゃんはそう言うと、お母さんの顔を見てにっこり笑いました。
すると、陽子ちゃんも同じクッキーをとって口に入れ、
「みっちゃん、おいしいね」
と言いました。
「うん。」
みっちゃんも返事をしました。
お茶を飲み終わると陽子ちゃんは、戸を開けて隣の部屋へ行きました。隣の部屋は子供部屋になっていて、おもちゃの箱が置いてありました。陽子ちゃんは、おいで おいでとみっちゃんに合図して
「みっちゃん、あそぼ」
と言いました。みっちゃんは、いいのかな?というような顔をしてお母さんを見ました。するとお母さんは笑いながら言いました。
「遊んでくれば。」
みっちゃんは片手でブンちゃんを抱いて陽子ちゃんの所へ行きました。すぐそこにお母さんが見えるので、みっちゃんも安心でした。
陽子ちゃんは、おもちゃの箱をドーンと倒しました。すると箱の中にあった沢山のおもちゃがガラガラと大きな音を立てて飛び出して来ました。お人形もぬいぐるみも、おもちゃのケーキ、ぶどうやりんご、お茶碗も、おなべ、ミニカー、アイロンまであります。みっちゃんは、自分の持ってない珍しい物が沢山あるので、キョロキョロと見ていました。
陽子ちゃんは、箱の奥に残った四角い箱を大事そうに持ってきました。そして箱のふたを開けると中の物を取り出しました。最初に聴診器、体温計、傷用の絆創膏、そして注射器でした。
陽子ちゃんは、聴診器を首にかけると
「わたしはお医者さんね。みっちゃんはママで、キティーは赤ちゃんね。赤ちゃん病気になっちゃったんね。だからみっちゃん、お医者さんに連れてきて。」
と言いました。
注射器を見ると、みっちゃんは なんだか胸がドキドキしてきました。それというのも、昨日、お母さんに連れられて、みっちゃんはお医者さんで予防接種の注射をしたばかりだったからです。
お母さんは、
「みっちゃんがね、悪い病気になって、高い熱が出ないように、強い体に変身させる為に注射するのよ。チクッと ちょっと痛いけど、すぐ終わるから みっちゃんなら頑張れるよね。」
と言いました。
でも ちょっと痛いと言うのを聞いて、いやだなと思いました。
「みっちゃん弱くてもいいもん。お熱出しても、がまんする。」
「ええー、だめだよ、病気になったら大変よ。ずうっと、ねんねしてなくちゃならないし。」
「でもみっちゃん行かない。お留守番してる。」
「だめなのよ、お医者さんが、どうしても、絶対にみっちゃんを連れてきて下さい、って言ったのよ。お母さんだって、小さい時注射したんだから。」
みっちゃんは仕方なくお母さんに連れられて、お医者さんへ行きました。待合室で待っていると、診察室に入った子が泣いています。みっちゃんも 何だか怖くなって、家に帰りたくなりました。椅子から降りて うろうろ歩いていると、お母さんが両手で抱いて、また椅子に座らせて、
「みっちゃん、大丈夫よ。腕に注射するけど、チクッとして1,2,3って3つ数えたら もう終わりになるからね。泣いて動くともっと痛くなるから、泣かないで頑張ってね。」
と言いました。
「大野さん。」
と看護士さんが名前を呼びました。ドアを開けると、診察室の中には男の先生が白い服を着て座っていました。先生はにこにこ笑いながら
「初めは、お腹と背中をモシモシしてみようか。」
と言って、冷たい聴診器をペタンペタンと背中や胸に当てました。
「大丈夫だね。じゃ、ちょっと ちくっとするよ。すぐ終わるからね。」
と言いました。みっちゃんは胸がドキドキ、ドキドキして、体がロボットになったように カチンと固まってしまい、動けなくなりました。
濡れた綿で腕をふくと 注射の針がささりました。痛くて体がビクッとふるえ、泣きそうになりました。でもみっちゃんは黙ったままでした。怖くて声も出なかったのです。
「はい、終わりだよ。強かったね、頑張ったねぇ。」
お医者さんと看護士さんが、かわるがわるほめてくれました。そしてみっちゃんは、シールをもらって帰ってきました。
陽子ちゃんは、その時のお医者さんのように、ブンちゃんをみっちゃんの手から取ると床に寝かせ、聴診器を胸に当てました。
「赤ちゃんはお熱がありますから、注射します。」
そう言うと陽子ちゃんは、注射器を手に持ちました。
「だめ。注射だめ。」
みっちゃんは大きな声で言いました。そして、びっくりしている陽子ちゃんに
「注射、痛い、痛い。ブンちゃんに注射しちゃだめ!」
そう言うとブンちゃんを抱いて、みっちゃんは大きな声で泣き出してしまいました。
「あ〜ん、わあ〜ん、わ〜ん」
「わあ〜ん、わぁ〜ん、わ〜ん」
みっちゃんの泣き声は止まらなくなってしまいました。
陽子ちゃんは驚いた顔のまま、ママの所へ走って行きました。みっちゃんのお母さんは、泣いているみっちゃんの所へ行くと、
「よしよし、注射痛かったんだよね。みっちゃん泣かないで頑張ったんだもんね。偉かったね、ほんとうに偉かったよね。」
そう言いながら、みっちゃんの背中を優しくなででくれました。
陽子ちゃんのママは
「お医者さんごっこは、終わりにしよう。さあ、注射器も聴診器もしまいましょう。」
そう言って、手早く箱に入れ、箱は引き出しの奥へとしまいました。
その後で、陽子ちゃんのママは、お皿に赤いりんごを切って持ってきてくれました。み
っちゃんはそれを見て、何だかやっと安心しました。そして皆でおいしいりんごを食べました。
そんな事があってからは、もう注射なんてこりごりだ。お医者さんごっこなんて絶対にやらないぞ、とみっちゃんは心に決めました。
美容院にて
何度か行きつけた美容院
パーマはかけないのですか と聞かれ
ええ と頷く
ストレートパーマをかけたら 落ち着きますが...
行く度にすすめられる
硬いわりに癖毛で まとまらない
気にしてはいるけれど
指輪もイヤリングも 飾るより
うっとうしくて 付けたくない
マニキュアさえしたくない
なんだか垢抜けない四十代
髪だって いつか白髪になれば
染めたいと思うかもしれない
だから 今は黒いままでいい
ありのままの自分だからこそ
包み隠すことなく
楽に生きられる
そう思いながら
大きな鏡の中で カットされていく
長かった髪も
短く変わっていく髪も
どちらも似合わないようで
自分の顔を直視できない
占 い
小 野 啓 子
小さな水晶の玉を見る
手をかざそうとも 見つめても
霊感などかけらもない私には
何も見えてこない
ただ何となく
天や地 山や川を守る八百萬の神
位牌に名のある代々の先祖たちの
見えない影に
包まれ 守られているという感じ
この古里で生まれ育った
日本人なのだ
私の前世はどこにいて
何をしていたのだろう
未来はどうなるのか
水晶玉は 何も答えてはくれない
そこに映し出されているのは
今 ここに在る自分だけ
ありのままの私なのだ
成 長
小 野 啓 子
もうじき十歳から十一歳の誕生日を迎える
背の割に
足のサイズが大きいのを気にしている
昨年から習い始めた琴
夏の発表会では足がふるえたと
初めて味わった緊張感
近頃興味を持ち始めた料理
本を見ながら一人で作りあげた
アップルパイ ゼリー ミネストローネ
他にもまだ意欲満々
ハイハイから 伝え歩き
立ち上がり 一人歩き
毎日毎日 成長していくのが
手に取るように分かった あの頃のように
表情の変わっていくのが見える
火や油を使う危険
不安を感じながら
冒険小説を読むように
ただ 子供のする事を見守っている
ごはん お代わりしてもいい?
遠慮しながら夕食時
俺はもういいや
夫は独り言のように呟く
子供茶碗の底に ほんの少しのご飯を
やっと食べていたのに
照れ笑いしながら
お代わりをよそって来た
真直ぐに伸びていってほしい
竹の子のように
心も体も


詩三篇 童話二篇(詩の↓)掲載
海 親離れ
あらゆる生命の源としてか まだまだ あどけない顔で
それとも胎内の記憶なのか 眠っている娘よ
友だちの事 勉強の事
座り込んだまま見ていると 色々話して気が晴れたのか
なつかしい思いに満たされてゆく
延々と続くおしゃべりで
海のない県から三時間かけて来た また十一時を過ぎてしまった
夕日の美しいという海岸
期待を裏切ることなく この胸から 旅立つ日が来ることを
水平線から雲までも 分かっているのか いないのか
ストロベリージャムのような色に染めあげ ゆったりと構え
落陽してゆく 取りあえず 目先の事だけ片付けている
大きく波が寄せる度 食事の大切さ
乾いた砂を 料理 洗濯 アイロンのかけ方
他にも教えておきたい事は沢山ある
優しく抱くように打ち寄せて
胸の中にある わずかな時間に
喧嘩のしこりや子供についての心配事 色々教え込もうとしながら
胃炎の痛みさえ 私自身も
少しずつ運び去り 流してくれる 気持ちばかりが空回りしている
今日の一日 家事を忘れ 親ならどんな動物だって
カモメのように 子が一人立ち出来るように教える
夕日と共に暮れてゆく その時間には限りがある
遠い遠い古里の安らぎの中で 親離れの時が来れば
甘えて寄って来る子に
激しく牙をむき
立ち向かい追い払う
それを境に
親と子から
一対一の個個として生きていく
例えば そんな猫の姿を
何度となく見てきた
優しくも厳しい
はっきりとした 親としての在り方を
日常
畑から庭に移植した
四葉の多いクローバー
緑の中から伸びた白い花
足元から
蜜の香りが鼻をくすぐる
晴れた日に
干した家族の布団を取り込みながら
感じるお日様の匂い
それでも
行った事の無い外国
お城や美術館
彫りの深い顔立ち 金色の髪
憧れは何時も
身近な暮らしとはかけ離れている
名声や冒険
体験する事の苦痛や苦悩より
見た目や言葉の響きに魅かれていく
普通という日常は
突然あっさりと
目の前から消え去っていくというのに
深い傷跡は残っても
痛みは忘れられるものなのか
明日も相変わらず暮らしている
たぶん それは
サーカスの綱渡りのようなものだと 気付かないだけの事なのだ
童話 みっちゃんとブンちゃん
一、わたしのブンちゃん
くりくり動く大きな目、まあるいお顔の、みっちゃんは二才の女の子です。
今日は大好きなお父さんに抱っこされ、お母さんと三人で、デパートに出掛けてきました。
お母さんは、お友達に赤ちゃんが生まれたので、お祝いに贈る物を見ていました。
その間、お父さんは、みっちゃんの手を引いて、おもちゃ売り場をあちこち見て回っていました。
可愛いぬいぐるみや人形が、沢山飾って置いてある所へ来たとたん、みっちゃんの足は、
床に吸い付いたように、ピタリと止まりました。
みっちゃんは、沢山の中の、一つのぬいぐるみだけを、じっと見つめています。それは、白地のつるつるした
布で出来た、キティーのぬいぐるみでした。ふわふわ、モコモコした布地のぬいぐるみの中でそれは一つだけ
しかありませんでした。
二段目の棚に、ちょうど、みっちゃんの目の高さに置いてありました。
それに気付かないお父さんは、他に行こうと、みっちゃんの手をひっぱりました。みっちゃんは、
「いやよ。」
と言って動こうともしません。
お父さんは、みっちゃんの顔を見て言いました。
「どうしたの?」
「あら、あれ。」
みっちゃんは、キティーのぬいぐるみを、指さして言いました。
「へえー猫のぬいぐるみか。」
大きく、こくりと、みっちゃんはうなずいて、お父さんを見ました。そして、みっちゃんが両手を伸ばして、
キティーを取った、その時でした。
みっちゃんより大きいかと思われる、三才くらいの女の子が走って来て、みっちゃんの前に立ち、みっちゃんの
手から、キティーをむんずとつかみ取り、来た方へと足早に歩いて行きました。
驚いて、小さな口をあんぐり開けたまま、みっちゃんは、女の子をずっと、目で追い続けました。
お父さんがみっちゃんの顔を見て、何か言おうとした瞬間、
「うあ〜ん、あーん、取っちゃった、取っちゃった、あ〜んあ〜ん。」
周りの人がびっくりして、ふり返るくらい大きな声で泣き出しました。泣きながらも、
女の子の方を、しっかり指さしています。
女の子も、女の子のお母さんも、みっチャンの方をふり向いて見ました。
みっちゃんが指さしているのを見ると、女の子は、キティーのぬいぐるみを、ギュッとしっかり胸に抱え込みました。
するとみっちゃんは、いつかスーパーで、男の子が床に寝転んでだだをこねていたように、床にひっくり返ると、
手足をバタバタさせ、泣きながら叫びました。
「みっちゃんの、みっちゃんの、うわぁーんうわぁーん」
女の子のお母さんは、その様子を見て、どういう事があったのかが分かりました。
「あの子が欲しいんだって、返してらっしゃい。」
「だめだもん」
女の子は、お母さんに取り上げられないように、キティーの耳を片方の手でつかみ、背中へかくしてしまいました。
「キティーは沢山持っているでしょう。これは買わないわよ。」
お母さんは、女の子の背中に手を回して、キティーを取ろうとしますが、女の子は、耳をギュッと、
しっかりつかんで離そうとしません。
「だめでしょ!離しなさい!」
お母さんは強く叱りました。女の子はキティーを離すと、わあっと泣き出してしまいました。
二人の泣き声は、おもちゃ売り場いっぱいに響きわたりました。
みっちゃんのお父さんは、ただ驚いて、その様子を見ていました。
女の子のお母さんは、キティーを持って、泣いているみっちゃんの所に来ると、
「ごめんね、はい。」
と、手に持たせてくれました。そして、女の子を抱っこして、行ってしまいました。
みっちゃんは、キティーを受け取ると、いっぱい涙をこぼしながら、ゆっくりと立ち上がりました。
みっちゃんの泣き声に、お母さんもかけ寄って来ました。
「どうしたの?」
「ああーびっくりした。でも、もう大丈夫。このぬいぐるみが欲しかったらしいよ。」
お父さんは、まるで夢から醒めたような顔でそう言うと、キティーのぬいぐるみを持った、
みっちゃんを抱き上げました。
「ブンちゃん、ブンちゃん。」
みっちゃんは、キティーのぬいぐるみを、しっかりと両手に抱いて言いました。
買う前から、もう名前まで付けてしまいました。
レジの店員さんにジロリと見られ、
「す、すいませんでした。」
お父さんはそう言うと、みっちゃんを抱いて、逃げるように出口の方へと歩いて行きました。
お母さんは、結局贈り物を買わずに、キティーのぬいぐるみのお金を払って、
お父さんとみっちゃんの後を追いかけました。
でも、それからというもの、どこに買い物に行っても、みっちゃんは、もう二度とあんなふうに、
だだをこねたりしませんでした。なぜって、床に寝転んで、手足をバタバタさせて、
頭もふって泣き叫ぶと、頭はクラクラ、目も回って、天井が落ちてくるんじゃないかと思ったからです。
みっちゃんは、もう毎日毎日、飽きることなくキティーのぬいぐるみのブンちゃんと、仲良く遊んでいます。
夜は夜で、ブンちゃんのママになったように、ちゃんと子守歌を歌い、ブンちゃんを寝かしつけてから、
次にお母さんに歌を歌ってもらい、みっちゃんが眠るのです。
キティーのぬいぐるみと、一緒に眠るその寝顔は、とても幸せそうに見えました。
二、にんじん、きらい
今まで平気で食べていた、にんじんを、みっちゃんは急に食べなくなりました。バターとお砂糖で甘く煮たにんじんも、
シチューやカレーの中のにんじんも、お母さんが口に入れて食べさせようとしても、
唇をキュッと結んで、横を向いてしまいます。
「にんじん食べると、とっても元気が出るのよ。ほうら食べてごらん、おいしいのに。」
お母さんがいくら言っても、全く食べようとはしませんでした。
ある時、お煮しめの中に、にんじんが入っているのを目ざとく見つけ、ちょっと嫌な顔をしました。
そして、さき程炬燵の上に座らせておいた、ブンちゃんの所へ走って行くと、片手に抱いて戻って来ました。
「ブンちゃん、にんじん、食べたいって。」
そう言い終らないうちに、お煮しめの皿に手を伸ばし、にんじんをつかみ取ると、
ブンちゃんの口に、クチャッと押し付けました。
お母さんが止める間もないくらいの早技でした。
おどろいて目を丸くしているお母さんに、
「ブンちゃん、おいしいって。おかわり、ほしいって。」
そう言うと、お皿の中のもう一つのにんじんを手でつかみ、また同じように、ブンちゃんの口に押し付けました。
ブンちゃんの口は、グチャグチャに潰れたにんじんで汚れてしまいました。
とても、おいしいと言っているようには見えません。目の下にはねた汁は、食べたくないと泣いているようでした。
「あーあ」
お母さんは半分あきれ顔で、ブンちゃんを洗面所に持って行き、石鹸を付け、口の周りをブラシでこすってやりました。
なんとか、きれいになったブンちゃん。
お母さんは、外に出て、庭に置いてある自転車のかごの中に座らせて乾かしました。
ブンちゃんはとても気持ち良さそうに、日なたぼっこをしているように見えました。
それからというもの、食事のたびににんじんが出ると、ブンちゃんは食べたくもないにんじんを、
無理矢理口に押し付けられ、洗われ、自転車のかごで日なたぼっこです。
さすがにお母さんも、にんじんを出さなくなりました。
ある日、お母さんと仲良しの、お友達の家に、お茶に呼ばれて行きました。
出掛ける前にお母さんは、生のにんじんを二本袋に入れました。
「いらっしゃい。こっちよ。」
お母さんのお友達は、外にいて、庭のすみの方から声を掛け、手招きしました。
そこには小さな小屋があって、中には真白くて、お目目の赤いうさぎがいました。
お母さんはみっちゃんに、にんじんを一本手渡すと、自分の持っているにんじんを、小屋の中にそっと入れました。
「みっちゃんも、にんじん入れて、うさぎさんにあげてね。」
お母さんは優しく言いました。
みっちゃんは、本物のうさぎを見るのは初めてでした。少し開けた戸の間から、恐る恐る手を入れて、
コトリとにんじんを落とすように入れました。
うさぎはすぐに、にんじんにかじりついて食べ始めました。コロコリと音をさせ、モグモグと口を動かすうさぎを、
みっちゃんは、まばたきするのも忘れ、食い入るように見ていました。
「おうちに帰る」
しばらくの間うさぎを見ていたみっちゃんはそう言うと、まだお茶もごちそうになっていないのに、
お母さんの手を取って、道路の方へ向かって歩き出しました。
お母さんはあわててお友達に挨拶して、あわただしく家に帰りました。
家に着くとみっちゃんは、台所にへ走って行き、冷蔵庫の中から残っていたにんじんを取り出すと、
いきなりガブリとかじり付きました。コロコリ良くかんで、もう一口ガブリ。
またもや、あわててお母さん。
「みっちゃん、にんじんは洗ってから食べましょうね。」
みっちゃんの口から、にんじんを取ろうとすると、
「やだ、みっちゃん、うさぎさんになっちゃったん。」
そう言って、にんじんを半分も食べてしまいました。
そんな事があってからは、
「みっちゃん、おやつはにんじんさん」
と言うようになりました。すると、お母さんもブンちゃんには、丸のままのにんじんを食べさせるまねをし、みっちゃんには、
「みっちゃんうさぎは、おしゃれさんよね。」
そう言って、にんじんを細長いスティックに切り、コップに立てて持って来ると、みっちゃんは上機嫌で食べました。
みっちゃんは生のにんじんが大好きな、とっても良い子になりました。
でも時々、返事をしてくれないブンちゃんに腹をたてて、ブンちゃんめがけ、にんじんを投げつけるのです。
そしてお母さんに叱られて、大きな声で泣き、本当にお目々の赤い見っチャンうさぎになるのでした。
沼田文学の会に妻が第九号より参加しました。
年一回発刊沼田の大きな本屋さんには置いてあります。文真堂 戸田書店 尾身書店etc.........
小野啓子詩集はここから